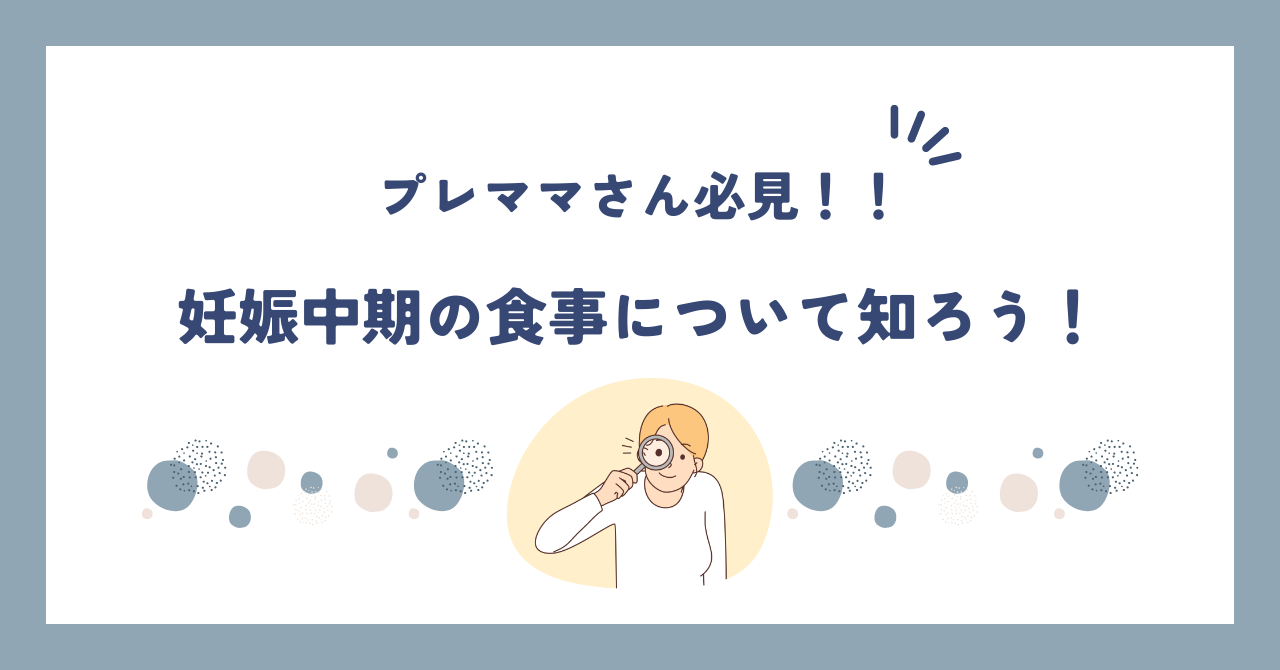はじめに
みなさん、プレママライフいかがお過ごしでしょうか。
妊娠中期に入った方は、つわりが落ち着いた人、まだ続いている人、さまざまだと思います。
前回の記事では主に「妊娠中の食事管理の基本」と、「妊娠初期の食事」について述べましたが、今回は妊娠中期から後期と特別な状況と食事管理についてまとめていきます。
少しでも参考になれば幸いです。無理せず栄養管理していきましょう。
妊娠中期の栄養管理
妊娠中期は母体と胎児が安定した時期ですが、引き続き栄養管理が重要です。この期間には特にカルシウムや鉄分、蛋白質といった栄養素が必要になります。ここでは、それぞれの栄養素の重要性について詳しく解説します。
妊娠中のカルシウム摂取の重要性
妊娠中は、赤ちゃんの成長に必要な栄養素をバランスよく摂取することが大切です。その中でもカルシウムは特に重要です。なぜなら、カルシウムは赤ちゃんの骨や歯の形成に欠かせない栄養素だからです。また、ママ自身の骨密度を保つためにもカルシウムは必要です。
妊娠中のカルシウム摂取量
日本人女性の平均的なカルシウム摂取量は、推奨量を満たしていないことが報告されています。妊娠中は特に注意が必要で、腸からのカルシウム吸収率が上昇するため、適切な摂取が求められます。
厚生労働省の「令和元年国民健康・栄養調査報告」によると、20代の女性は1日408mg、30代は406mgのカルシウムを摂取しているとのこと。これは推奨量には達していません。妊娠中期のカルシウムの摂取量は、1日当たり約650mgが推奨されています。
カルシウムを摂るための食事の工夫
以下は、カルシウムを摂るための食事のアイデアです。健康的な妊娠をサポートするために、意識的にカルシウムを摂取しましょう!
1. 乳製品
牛乳、ヨーグルト、チーズなどの乳製品はカルシウムが豊富です。1日に2〜3杯摂ることを目指しましょう。
2. 魚介類
サケやサバなどの魚介類にもカルシウムが含まれています。積極的に摂りましょう。
3. 緑黄色野菜
小松菜、ほうれん草、ひじきなどの緑黄色野菜にもカルシウムがあります。
4. 豆類
納豆や豆腐も良い選択肢です。
鉄分の重要性
鉄分はヘモグロビンというタンパク質の一部で、赤血球の中に存在します。赤血球は酸素を体中に運ぶ役割を果たしています。また、妊娠中は母体の血液量が増加し、赤ちゃんの成長に必要な酸素を供給するため、通常よりも多くの鉄分が必要です。
鉄分不足は貧血を引き起こします。貧血は疲労感、めまい、頭痛などの症状を引き起こすことがあります。さらに、赤ちゃんの脳や臓器の発育にも鉄分が必要です。
鉄分の摂取量
妊娠初期では一日2.5mg、妊娠中期以降は一日15.0mgの鉄分を摂るのが理想です。
鉄分はヘム鉄(肉や魚)と非ヘム鉄(野菜や豆類)の両方をバランスよく摂取することが大切です。
鉄分を摂る食品
主な鉄分を含む食品とその含有量を表にまとめました。
| 食品名 | 目安の量 | 鉄含有量(mg) |
| 豚レバー | 焼き鳥 1串 | 3.9 |
| 鶏レバー | 焼き鳥 1串 | 2.7 |
| かき(むき身) | 約5個 | 1.4 |
| 牛もも肉(赤肉) | 約1枚 | 1.9 |
| めじまぐろ | 切身 1切 | 1.3 |
| あさり(むき身) | 約10個 | 1.1 |
| しじみ(むき身) | 約10個 | 1.1 |
| ひじき(乾燥) | 大さじ2/3 | 5.5 |
| 大豆(乾燥) | 1/3カップ | 3.8 |
| 小松菜(生) | 1/3束 | 2.0 |
| 切干大根 | 1/4カップ | 2.0 |
| ほうれん草(生) | 1/3束 | 1.4 |
| 高野豆腐 | 1個 | 1.4 |
| 納豆(中) | 1パック | 1.3 |
妊婦とタンパク質の関係
たんぱく質とは、20 種類の L–アミノ酸がペプチド結合してできた化合物です。たんぱく質は他の栄養素から体内で合成できず、必ず摂取しなければなりません。したがって、たんぱく質は必須栄養素である。たんぱく質を構成するアミノ酸は20種類あると言われています。ヒトはその20 種のうち、11 種を他のアミノ酸又は中間代謝物から合成することができますが、それ以外の9種は食事から直接に摂取しなければなりません。それらを必須アミノ酸といいます。必須アミノ酸はヒスチジン、イソロイシン、ロイシン、リシン、メチオニン、フェニルアラニン、トレオニン、トリプトファン、バリンです。
妊娠中期には新しい細胞の生成が続くため、タンパク質の摂取が重要です。タンパク質は血液やホルモンの生成、筋肉の発達にも役立ちます。鶏肉や魚、大豆製品、ナッツ類が良質なタンパク質源です。1日あたりの目安量を守り、バランスよく摂取しましょう。
※https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000586557.pdf
適正な体重管理の方法
妊娠中期は体重が増えやすい時期です。過剰な体重増加は妊娠糖尿病や高血圧のリスクを高めるため、適切な体重管理が必要です。栄養バランスの取れた食事と適度な運動を心掛け、定期的に体重を管理しましょう。
妊娠前の体重による目安量
妊娠中の体重増加は、妊娠前のBMI(Body Mass Index)によって適切な体重増加量が決まります。
通常、妊娠期間を通して体重は8~12㎏程度増えることが一般的です。
この増加は、赤ちゃんの重さ(3kg)、胎盤(500g)、羊水(500g)、子宮(1kg)、乳房や体脂肪の増加(2kg)、全身の血液量や水分(2kg)によるものです。
妊娠中の体重増加は、胎児の発育や成熟のために自然なことです。
BMI(Body Mass Index)の算出方法は以下の通りです。
BMI = 体重kg ÷ (身長m)2
例えば、妊娠前が低体重(BMI18.5未満)の場合は、12~15kgの増加が目安です。
| BMI範囲 | 肥満度 |
|---|---|
| 18.5未満 | 低体重(やせ) |
| 18.5以上〜25未満 | 普通体重 |
| 25以上〜30未満 | 肥満(1度) |
| 30以上〜35未満 | 肥満(2度) |
| 35以上〜40未満 | 肥満(3度) |
| 40以上 | 肥満(4度) |
| 妊娠前体格 | 体重増加量の目安 |
| 妊娠前BMIが18.5未満(低体重)の場合 | 12~15㎏ |
| 妊娠前BMIが18.5以上25未満(普通体重)の場合 | 10~13㎏ |
| 妊娠前BMIが25以上30未満(肥満度1度)の場合 | 7~10㎏ |
| 妊娠前BMIが30以上(肥満度2度以上)の場合 | 個別対応(上限は5㎏までが目安) |
適切な食事
食事はバランスよく摂ることが大切です。野菜や栄養素を豊富に含む食材を選びましょう。
つわりの時期は食べられるものを優先し、過度な制限は避けましょう。
適度な運動
妊娠中期から運動を取り入れることがおすすめです。ウォーキングや水中エクササイズなど、無理のない運動を心がけましょう。体重管理はダイエットではないため、食事管理を中心に行い過度な運動には注意が必要です。
自己管理と相談
妊娠がわかった時点から体重管理を意識しておきましょう。
医師や助産師と相談しながら、適正な体重増加を目指しましょう。アプリなどでも簡単に記録することができるので活用できるといいですね。
適切な体重管理は、母子の健康を守るために大切なことです。3 ご注意点や具体的なアドバイスは、専門家と相談しながら進めてくださいね。
妊娠後期の食事
妊娠後期は母体と胎児のためにさらに多くのエネルギーと栄養素が必要です。この期間の適切な栄養管理は出産準備と産後の回復に非常に重要です。ここでは、エネルギー補給や必須栄養素、食生活のポイントについて詳しく説明します。
エネルギー補給と適切な食事
妊娠後期にはエネルギー需要がさらに増加します。バランスの取れた豊富な食事を心掛け、1日の摂取カロリーを増やしましょう。例えば、全粒穀物、果物、野菜、タンパク質を豊富に含む食品を選ぶことが重要です。小分けにして食事回数を増やすことで、胃の負担を減らしながら栄養を確保できます。
妊娠後期の必須栄養素
妊娠後期には特定の栄養素が特に重要です。鉄分は貧血を防ぎ、カルシウムは赤ちゃんの骨を強化します。オメガ-3脂肪酸は赤ちゃんの脳の発達をサポートし、ビタミンDはカルシウムの吸収を助けます。これらの栄養素をはじめ、多様な食品を取り入れることが大切です。
産前準備のための食生活
出産を控えたこの時期は、産前準備としてバランスの取れた食生活を心掛けることが重要です。エネルギー密度の高い食品や、ビタミン・ミネラルが豊富な食品を選ぶようにしましょう。また、食物繊維を多く含む食品を摂取して、便秘を予防することも大切です。
むくみと食事の関係
妊娠後期にはむくみが生じやすいため、塩分の摂取量に注意することが重要です。塩分過多がむくみの原因となるので、薄味の食事を心掛けましょう。さらに、カリウムが豊富なバナナやじゃがいもを摂取することで、むくみの軽減が期待できます。
産後の体力回復を助ける食事
出産後の体力回復には、栄養バランスの取れた食事が欠かせません。蛋白質を中心に、ビタミンやミネラルを十分に摂取することで、体力の回復をサポートします。特に、鉄分やカルシウムが豊富な食品を積極的に取り入れるようにしましょう。
特別な状況と食事管理
妊娠中にはさまざまな特別な状況が発生することがあります。妊娠糖尿病やアレルギー、ベジタリアン妊婦、および双子妊娠など、それぞれの状況に適した食事管理が必要です。ここでは、その具体的なガイドラインについて解説します。
妊娠糖尿病と食事療法
妊娠糖尿病は、妊娠中に初めて発見または発症した糖代謝異常で、血糖値が上がりやすくなったり、上がった血糖を適切な範囲まで下げにくくなる状態を指します。妊娠糖尿病の治療では、母体と胎児に異常が起きないように血糖値を厳重にコントロールすることが大切です。食事療法はその基本です。低GI食品を中心に選び、食事を小分けにすることで血糖値の急激な上昇を防ぐことができます。また、甘いものや高脂肪食品は避け、バランスの取れた食事を心掛けることが大切です。
妊娠糖尿病の食事療法について、以下のポイントをまとめます。
1. 時間を規則正しく
毎日同じ時間に食事を摂ることで血糖値の安定を図りましょう。
2. 量をムラなく
1日の適正エネルギー量を3等分し、朝・昼・夜に分けて食べることで血糖コントロールをサポートします。食事の量が多すぎても少なすぎても、よくありません。一食当たりの量が少ない場合は、間食を挟むこともあるかと思います。そのエネルギー量も1日の適正エネルギー量の中に収めるよう、計算に入れるのを忘れないようにします。
妊娠中のエネルギー必要量は、個々の妊婦さんの体重、身長、活動量、妊娠週数などによって異なりますが、一般的な目安として、以下のようになります。
| 妊娠初期 | 通常のエネルギー必要量にほぼ変化はありません。妊娠前と同じく、基礎代謝量と活動量を考慮して摂取カロリーを調整します。 |
| 妊娠中期 | 妊娠中期には、妊娠前と比べて約300~350kcal/日の追加エネルギーが必要です。これは、胎児の成長や胎盤の形成に必要なエネルギーです。 |
| 妊娠後期 | 妊娠後期には、約450~500kcal/日の追加エネルギーが必要です。胎児の成長が急速に進むため、エネルギー摂取量を増やすことが重要です |
具体的なエネルギー必要量は、医師や管理栄養士と相談しながら決定することをおすすめします。
3. 内容をバランスよく
一般的には1日の適正エネルギー量の配分は炭水化物50~60%、たんぱく質15~20%、脂質20~25%といわれます。つまり主食(炭水化物)、主菜(タンパク質)、副菜(野菜や海藻類)をバランスよく摂取することが必要です。
妊娠糖尿病の場合、血糖値の目標値は以下の通りです。
早朝空腹時血糖:95mg/dL以下
食前血糖値:100mg/dL以下
食後2時間血糖値:120mg/dL以下
これらのポイントを守ることで、健康な妊娠をサポートできます。
アレルギー対策の食事
特定の食物アレルギーを持つ妊婦は、アレルゲンを避けるための食事管理が必要です。食品の成分表示を注意深く確認し、安全な代替食品を選ぶことが重要です。また、医師や栄養士と連携して、必要な栄養素を漏れなく摂取できるように対策を練りましょう。
ベジタリアン妊婦の栄養管理
ベジタリアン妊婦は動物性食品を摂取しないため、特定の栄養素が不足しやすいです。蛋白質は大豆製品やナッツ類、鉄分はレンズ豆やほうれん草、ビタミンB12は強化食品やサプリメントで補うことが望ましいです。バランスの取れた植物性食品を多様に摂取することが鍵です。
双子妊娠の場合の栄養管理
双子を妊娠している場合、母体の栄養需要はさらに高まります。蛋白質、鉄分、カルシウムを含む食品を積極的に摂取し、エネルギーを増やすことが重要です。また、適切な水分補給と、食事の質を高める工夫が必要です。医師や栄養士と相談しながら食事計画を立てましょう。
まとめ
妊娠期間中の食事管理は、母体と胎児の健康を維持するために極めて重要です。妊婦に必要な栄養素や摂取方法について理解し、適切な食事を選ぶことで、妊娠初期のつわり対策や葉酸、妊娠中期のカルシウムと鉄分、妊娠後期のエネルギー補給など、各時期に応じた栄養補給が可能になります。特に避けるべき食品や飲み物を把握することで、健康リスクを軽減できるでしょう。
特別な状況に応じた食事管理も大切です。個々の体調や状況に応じた適切なサプリメントの選定と共に、体力回復のためのアプローチも忘れずに実践することが望まれます。適宜医師や助産師さんに相談し、状況に応じた対応ができるといいですね。
最後に、適切な情報と注意を払いながら食事管理を行うことで、母体と胎児の健康を最優先に考えた最善の結果を得られます。これらの知識を活用し、安心で健康な妊娠期間を過ごしましょう。